群馬県と栃木県の県境付近、足利市の北方には「石尊山」「行道山浄因寺」「大岩山」「岩刻の毘沙門天」「両崖山」など巨石に関係した
地名や名刹が並び、直径10Kmにも及ぶ大きなメガリス(巨石遺構)文化圏を形成しています。その北縁にその名もずばりの
「名草(なぐさ)の巨石群」があります。前橋の親類を訪ねた帰路、以前から行きたいと思っていた「名草」に足を向けました。
と言っても、前橋から国道50号線を東進し、桐生バイパスの原宿南までが40Kmもある行程です。渡良瀬川を越えて葉鹿町の郵便局で
名草に行く道を尋ねると、怪訝な顔で問い返されました。「名草…ですか。」「結構ありますよ。普通のクルマではちょっと厳しいんではないかあ…」。
確かにそうだ。地元の人から見れば普段生活しているところから10Km以上も山奥の名草にクルマでいくなんて…と思うのも無理はありません。
幅員2mもあれば舗装路で有れ砂利道で有れごく当たり前のように山の中にクルマで入る私なのであります。
松田川に沿って約20分北上し県道219号を中井で右に折れればやがて勘定谷戸というところで「←名草巨石群」の小さな看板が見えてきます。
名草巨石群の中心には…やはり、っと言った感じで厳島神社(名草弁天)が臍としてあり、厳島神社の境内を巨石が飾っているという期待にかなった優れものの巨石群が
そこにはありました。駐車場を備えた茶店の横から厳島神社の参道が続きますが、最初そうとはしらず、厳島神社の参拝は後にして、
さらに細い山道をクルマで巨石に向かいました。結局は厳島神社の境内をぐるりと裏山から降りてきた格好になりましたが、結果的には
厳島神社奥の院をも確認することができ、鹿島神社の御はからいに感謝することしきりなのでありました。
今回は写真がかなりありますので、2部作にわけ、まず第1作「名草巨石群1」をお届けします。あいもかわらず、私のページはダウンロード
に時間がかかりますが、お待ちになるだけのものはご覧頂けると確信します。今回はBGM無しです。どういうわけか名草の巨石群はサウンドの
イメージが湧きません。「静謐なる佇まい…」とでも申しましょうか…。
1996泰山記
2010 高精細画像に置換え+補足
2010年のリニューアルで、厳島神社入り口から名草弁財天およびその背後の巨石群を探訪するコースにて紹介します。
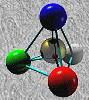 Gainendesign-Labo.
Gainendesign-Labo.




















