古峰ヶ原心象紀行2;巨石の森美術館-1
Copyright(C) 2001 by Taizan
泰山の古代遺跡探訪記 Presented by…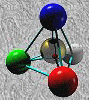 Gainendesign-Labo.
Gainendesign-Labo. |
------------------↓本サイト主催の概念デザイン研究所が無料公開しているエッセイの PR↓------------------ ※概念デザイン特別エッセイ集2021;大谷選手など今気になる話題の概念分析が盛りだくさん! |
古峰ヶ原心象紀行2;巨石の森美術館-1
Copyright(C) 2001 by Taizan
泰山の古代遺跡探訪記 Presented by…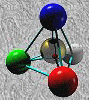 Gainendesign-Labo.
Gainendesign-Labo. |
------------------↓本サイト主催の概念デザイン研究所が無料公開しているエッセイの PR↓------------------ ※概念デザイン特別エッセイ集2021;大谷選手など今気になる話題の概念分析が盛りだくさん! |
古峰神社の脇を抜けて古峰ヶ原へと続く道はつづら折れの細い舗装道路である。途中お定まりの”ゲート”に出くわす。殆どの人はここでクルマを捨てて、残りの山道を しばらく歩くことになる。運良くその日はゲートの半分が開いていた。本当はゲートなどあって無いようなものだ。要するに簡単に出入りがしにくい様に工夫されて いるわけである。こういう仕掛けは結構”アヤシイ”山には多い。俄かづくりのゲートは言わば”余り立ち入らせないための看板”のようなもので、”結界”とは違う。明らかに人為的なバリアである。たまたま「どうぞ」といわんばかりに開いていたゲートを そのままクルマでやり過ごし、工藤さんと私は古峰ヶ原へと向かった。
舗装道路が途切れた先が目指す古峰ヶ原である。クルマの腹をガリっと大きくこすりながら、古峰ヶ原の横にクルマを止めた。 古峰ヶ原は湿原のひとつで、周囲をぐるりと低い山で囲まれた、盆地状の地形をしている。秋の古峰ヶ原一体は既に枯草で一面覆われていた。久しぶりに見る穏やかな風景 だった。…しかし、やがて私の脳裏にまた違った思いが巡っていた。
今まで訪ねてきたピラミッドや巨石山の風景とはあまりにも違う景色が眼の前にある。その情感の好ましさとは裏腹に、巨石との接点がどうしても見当たらない。 そのギャップがたまらなく不思議でしょうがなかった。…とは言っても既に工藤さんが訪ねている巨石の庭だ。巨石があることは間違いないのだが…
Copuright(C)2001 Taizan「…で、巨石の山はどの山なの?」との問いに、工藤さんは左手前方の小山を指差した。山は手が届くほどに低い。少なくとも私にはそう見える。果たしてこの山が 巨石の山なのか…。その山へ続く小道はまるでピクニック用のそれである。一体どこから巨石ゾーンが始まるのだろうか。
偶然そこに居合わせたほかの数人のグループを 見送りながら、われわれも、その小山の山頂を目指して歩き始めた。その穏やかな”ピクニック・ロード”はものの数百mも行かぬうちに、急激に様相を変え始めたのである。湿原の脇に止めた車の影が視界から消え始めるころから山の”気”が 変化してきた。…と言っても山の天気が変わったわけではなく、ムードがシフトし始めたということである。
『この雰囲気ならば巨石の匂いを感じられる』…そんな思いを 抱きながら少し進むと、突然のごとく”銀色の鳥居”が出現した。『銀!…か。』妙な鳥居ではある。その妙な銀色の鳥居を過ぎると、それこそ待ち構えていたかのように夥しい巨石群が我々を出迎えたのである。参道(基本的に巨石山の頂上には本殿があり、山道は参道 のことが多い)の左右に屹立する巨石に見入っていると、既に一度踏み入れている工藤さんが「もっと奥に凄いものがありますよ」と促してくる。我々は参道を大きく 外れて巨石が転がる道無き道を進みながら山頂に向けて探索行を始めた。
岡山の吉備地方にある鬼ノ城に瓦礫の河のような構造があるが、それを数倍ほどの規模にした巨石の河原が目に入って来た。数m規模で10トン以上はあると思われる 夥しい数の巨石が、まるで氷河のように山頂から山腹に掛けて流れ落ちているように並んでいる。その圧倒的な迫力におもわず「おーっ」と嘆息が出てしまう。
2000泰山記
2010 高精細画像に置換え+補足
Copuright(C)2001 Taizan
直径3mほどはある円盤状の巨石が土に突き刺さっている。鏡石にしては余りにも薄い。むしろ御幣持ちのような形状をした”笠石”の一種なのではないかと思われた。 それにしても見事な造形美に撫で回すことしきりなのであった。
Copuright(C)2001 Taizan
暫くして冷静さを取り戻した私の耳に何やら心地よい音楽が聞こえてきた。「何か聞こえない?」と工藤さんと一緒に耳を澄ましてみる。 するとどうだろう。オルゴールのような澄んだ音色が聞こえてくるでは無いか。音源を探ってみるとそれは我々の足下の巨石から聞こえてきている。 おもわず我々は顔を見合わせた。
もう一度巨石の下に神経を集中する。…するとそれは更に奥の巨石の下方から聞こえてきている。
「水だ!水が流れている!」…それも確かに、水琴窟のような澄んだ高音のせせらぎの音なのだ。こんな小山のしかも巨石の河原の下に水が流れている。二人は予想もしていなかった 音楽での出迎えに気を良くしながら、さらに奥へと進んで行った。