関東平野の中にぽつんと聳え立つのが、特集4で取り上げた霊峰筑波山です。
その北に少し背は低くなりますが、筑波山と同様に霊山として古くより
尊崇され、行場として有名なのが加波山です。加波山の情報は昨年
私の知人である真壁町の鈴木正徳氏からもたらされました。
鈴木氏から送られてきた真壁町の歴史民族資料館作成の「石とくらし」
という厚めのパンフレットには、筑波山をしのぐ巨石の写真が数多く載っていました。
今回、1年間の想いをこめて加波山の巨石群を探訪してきました。
珍しくどしゃ降りの雨の中、鈴木正徳氏にも同行をして頂き、加波山の凄さを堪能してきました。
国学者、平田篤胤は江戸時代に仙童寅吉の助けを借りて、天狗の研究に情熱を
注ぎましたが、平田篤胤によれば、筑波山塊には十三天狗が、この加波山には
何と四十八天狗がいたとのこと。霊力では加波山は関東随一の場所と言えます。
加波山中には夥しい数の巨石や磐座が存在しますが、今回は加波山頂上にある
加波山神社の周辺を中心に探訪記を記します。山中は雨に煙ってまさに
幽玄郷そのものでした。圧巻は頂上にあった太陽石と思しき巨石で、
たつ割れ山の太刀割り石と同様にまっぷたつに割けていたことです。
加波山はその周辺にある足尾山等の山々と呼応し、かつ神社の存在があり、
巨石群の頂上付近での配置から、筑波山と同様にヒラミツトに違いありません。
関東平野のど真ん中にこのような巨大なヒラミツトシステムが形成されて
いたことに改めて感動すると同時に、自らの不勉強さを思い知らされました。
それではほんの一部の紹介ですが、茨城は真壁町の加波山をお楽しみ下さい。
1997泰山記
2010 高精細画像に置換え+補足
2001年の再探訪時の写真を追加して再編集を2010年に実施。講談社発行のウオーキングマガジン2001年10月号の取材案内のため加波山を再訪した。1996年のときには加波山頂上付近で雨になったため来た道を引き返した。2001年のときには9合目の登山口までクルマで行き、そこから山頂経由で加波山事件で有名な旗立石まで行った。1996年当時の写真は霧雨によるピンボケが多いので、なるべく同じ場所については2001年版に差し替えた。小さい画像はデジカメ映像なのだが、なにせ1996年当時の低解像度カメラなのでこれが限界。
筑波山も素晴らしいが、加波山もまた非常に良い。双方ともにピラミッド山の要件をしっかりと備えた美しい山である。前者が”ハレ”の舞台ならば、後者の加波山は
”ケ”の舞台であろう。前者が光ならば後者は影、同じく陽ならば陰。そういう感じがする。個人的には加波山の方がしっとりと重くて好きである。筑波山と加波山のセットで関東平野の臍になっていると思う次第である。
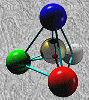 Gainendesign-Labo.
Gainendesign-Labo.






































